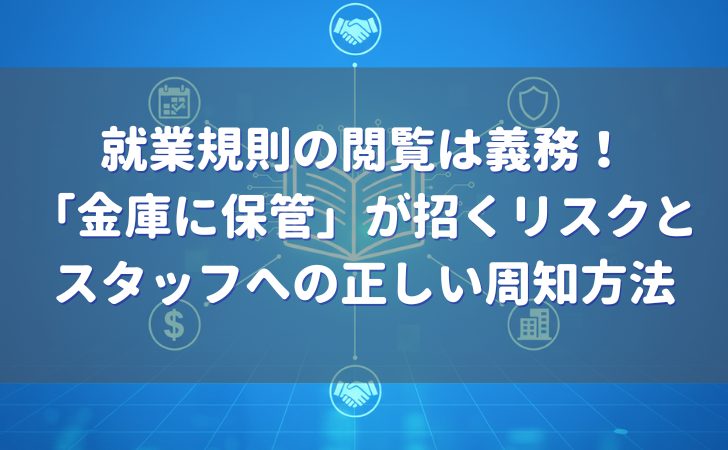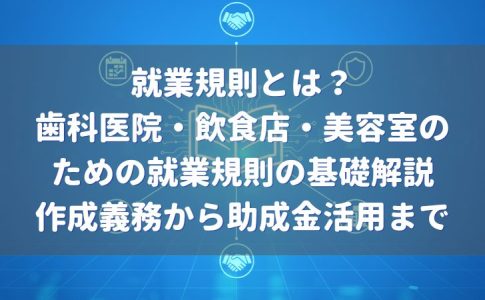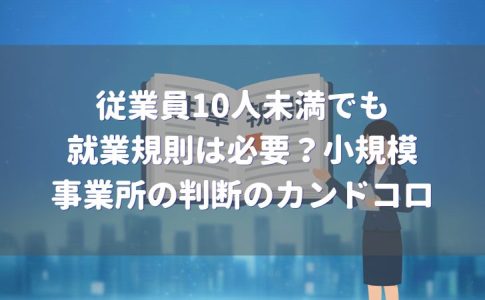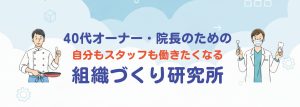神戸市で飲食店、美容室、歯科医院を経営されているオーナー、院長先生で、もし就業規則の閲覧に関して、
「就業規則は大切なものだから金庫や鍵付きの書棚に保管している」
「スタッフから見たいと言われたら見せればいい」
もし、このように考えていらっしゃるなら、ちょっと待ってください。
実は、就業規則の閲覧は法律で義務づけられており、金庫に保管して必要な時だけ見せるという方法では、周知義務違反として罰金を科される可能性までもあるんです。
そこでこの記事では、社労士×生成AI活用アドバイザーの視点から、就業規則の正しい周知方法と金庫保管が招くリスクについて詳しく解説します。
この記事でわかること
- 就業規則の閲覧義務とその法的根拠
- 金庫保管が招く具体的なリスク
- 小規模事業所でも実践できる正しい周知方法
目次
就業規則の閲覧義務とは?基礎知識を確認
就業規則の閲覧義務の法的根拠
就業規則の閲覧義務は、労働基準法第106条に明確に定められています。
法律では、使用者は就業規則を「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」と規定してあり、労働者に周知させなければならないとされています。
つまり、就業規則はスタッフが「見たい時にいつでも見られる状態」にしておく必要があり、経営者の許可を得なければ閲覧できないような状態は認められません。
金庫や鍵付きの書棚の場合、
経営者や一部の人間だけが開閉できる→×
全スタッフが自由に開閉できる→〇
なぜ就業規則の周知が重要なのか?
就業規則の周知が重要な理由は、大きく3つあります。
1. 法的効力の発生要件
周知されていない就業規則は、法的効力を持ちません。つまり、金庫に保管されたまま従業員が自由に見られない状態では、その就業規則に基づいて懲戒処分などを行うことができないのです。
2. 労務トラブルの予防
労働時間や休暇、給与計算のルールなどを明確に周知することで、「知らなかった」「聞いていない」というトラブルを未然に防ぐことができます。
3. 組織の透明性向上
ルールが明確に周知されている職場は、スタッフの安心感につながり、定着率の向上にも寄与します。
対象となる従業員の範囲
就業規則の周知義務は、正社員だけでなく、パート・アルバイトを含む全スタッフが対象です。
雇用形態に関わらず、すべてのスタッフが自由に就業規則を閲覧できる環境を整える必要があります。
特に飲食店や美容室、歯科医院のように、多様な雇用形態のスタッフが働く職場では、この点を見落としがちですので注意が必要です。
複数の店舗や分院がある場合は、本店・本院だけではなく、それぞれの店舗・分院で閲覧可能な状態にしておく必要があります。
就業規則の「金庫保管」が招く3つの深刻なリスク
リスク1:労働基準法違反による罰則
就業規則を金庫に保管し、スタッフが自由に閲覧できない状態は、労働基準法第106条違反に該当します。
この違反が発覚した場合、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、労働基準監督署からの是正勧告や指導の対象となり、企業の信用が損なわれるリスクもあります。
リスク2:就業規則の効力が認められない
前述したように、より深刻なのは、周知されていない就業規則は法的効力を持たないという点です。
これにより、以下のような問題が発生します。
- 懲戒処分ができない: スタッフの問題行動があっても、就業規則に基づく懲戒解雇や減給などの処分を科すことができません。
懲戒処分は罪刑法定主義の考え方が使われるため、あらかじめ、どのような行為が懲戒処分の対象となり、どのような処分が下されるのかが周知されておく必要があります。
- 労働条件の主張が困難: 就業規則に記載された労働時間や休暇のルールを主張できず、個別の労働契約内容のみが有効となります。
- 賃金規程の適用不可: 給与や手当に関する規定も無効となる可能性があり、スタッフから予期せぬ請求を受けるリスクがあります。
リスク3:労使トラブルの増加
就業規則が自由に閲覧できない状態は、従業員の不信感を招きます。
「何か都合の悪いことが書いてあるのでは?」
「本当は違法な労働条件なのでは?」
このような疑念が生まれると、労使関係が悪化し、些細なことでもトラブルに発展しやすくなります。
結果として、優秀なスタッフの離職や、労働基準監督署への相談・通報につながる可能性もあるのです。
実際に私が関与した企業さまでは、就業規則が支店長の鍵付きのキャビネット内に保管されていたため、固定残業手当は無効で、残業代の未払いがあると元従業員が依頼した弁護士から主張されました。
小規模事業所でも実践できる!正しい周知方法
法律で認められている3つの周知方法
労働基準法施行規則第52条の2では、以下の3つの方法が認められています。
方法1:作業場への掲示・備え付け
就業規則を冊子などにまとめ、スタッフが手に取って自由に見られる場所に設置する方法です。事務所だけでなく、休憩室など誰もが立ち寄る場所でも構いません。
方法2:書面での交付
入社時や就業規則変更時に、スタッフ全員にコピーを配布する方法です。ただし、持ち出しによる情報漏洩のリスクや、配布漏れの管理が課題となります。
方法3:電子データでの共有
パソコンやタブレットで常時閲覧できるようにする方法です。社内ネットワークやクラウドサービスを活用すれば、最新版の管理も容易です。
飲食店におすすめの周知方法
飲食店では、ホールとキッチンでスタッフが分かれていることが多いため、バックヤードの休憩スペースにファイルで設置するのが効果的です。
また、シフト制で出勤日がバラバラの場合は、タブレット端末を1台用意し、電子データで閲覧できるようにすると、いつでも確認できて便利です。
美容室におすすめの周知方法
美容室では、スタッフルームにクリアファイルに入れた就業規則を常備し、誰でも手に取って読める状態にしておくのが基本です。
スマートフォンでアクセスできるクラウドストレージ(Google DriveやDropboxなど)に保存し、全スタッフに共有リンクを送る方法も効果的です。
歯科医院におすすめの周知方法
歯科医院では、スタッフルームの書棚に就業規則ファイルを設置し、朝礼や定期ミーティング時に内容を確認する機会を設けると効果的です。
院内LANがある場合やは、共有フォルダに格納し、受付や診療室のパソコンからいつでも閲覧できるようにする方法も推奨されます。
全員が使えるパソコンに保存しておく方法も有効です。
就業規則の周知に関してよくある誤解と注意点
❌ 間違い: 「見たいと言われたら見せればいい」
✅ 正解: 従業員が自発的に、いつでも閲覧できる状態にしておく必要があります
❌ 間違い: 「労働基準監督署に届け出ているから問題ない」
✅ 正解: 届出と周知は別の義務です。届出だけでは周知義務を果たしたことになりません
❌ 間違い: 「正社員にだけ見せればいい」
✅ 正解: パート・アルバイトを含む全スタッフが対象です
就業規則周知のチェックリスト
以下のチェックリストで、自社の周知状況を確認してみましょう。
すべてにチェックが入らない場合は、早急に改善が必要です。
社労士が教える就業規則管理の労務ポイント
周知の証拠を残すことの重要性
万が一、労使トラブルが発生した際に「就業規則を周知していた」ことを証明できるよう、周知の証拠を残しておくことが重要です。
- 就業規則を設置している場所の写真を撮影・保管する
- 新入社員に対して就業規則の説明を行った記録を残す
- 電子データでの周知の場合は、アクセスログを確認できるようにする
- 就業規則変更時の説明会実施記録を保存する
就業規則変更時の注意点
就業規則を変更した場合も、同様に周知する義務があります。
変更内容をスタッフに説明し、何がどう変わったのかを明確に伝えることで、誤解やトラブルを防ぐことができます。
特に労働条件の不利益変更を伴う場合は、従業員の理解を得るためのプロセスが非常に重要です。
小規模事業所でも作成義務がある場合とない場合
常時10人以上のスタッフを雇用している事業所は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
ただし、10人未満の事業所でも就業規則を作成することは推奨されます。
なぜなら、明確なルールがあることで労使トラブルを予防でき、スタッフが安心して働ける環境を作ることができるからです。
また、10人未満でも就業規則を作成した場合は、周知義務が発生することを忘れないでください。
就業規則の周知についてよくある質問
まとめ:就業規則は「働きたくなる組織」の基盤
本記事では、就業規則の閲覧義務と金庫保管が招くリスク、正しい周知方法について詳しく解説しました。
重要ポイント
- 就業規則の周知は労働基準法で義務付けられており、違反すると30万円以下の罰金が科される可能性がある
- 金庫保管や許可制での閲覧は周知とは認められず、就業規則の効力自体が失われるリスクがある
- 小規模事業所でも実践できる周知方法があり、業種に応じた工夫が可能
就業規則を正しく周知することは、単なる法令遵守ではありません。
ルールが明確で透明性のある職場は、スタッフの安心感と信頼を生み、「自分もスタッフも働きたくなる組織」の基盤となります。
神戸市の小規模事業所の皆様が、労務トラブルのない健全な職場環境を実現できるよう、今日からできることから始めてみてください。
🎯 就業規則でお悩みの経営者の方へ
無料相談実施中!
✅ 現在の就業規則が法令に適合しているか30分でチェック
✅ 小規模事業所に最適な周知方法をご提案
✅ AI活用による就業規則の効率的な管理方法もアドバイス
【神戸市の小規模事業所様向け特別サポート】
初回相談無料
当事務所では、飲食店・美容室・歯科医院など、神戸市内の小規模事業所に特化した就業規則の作成・見直しサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。