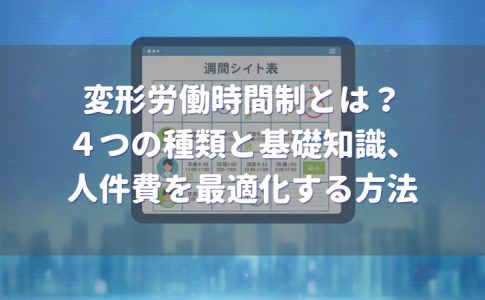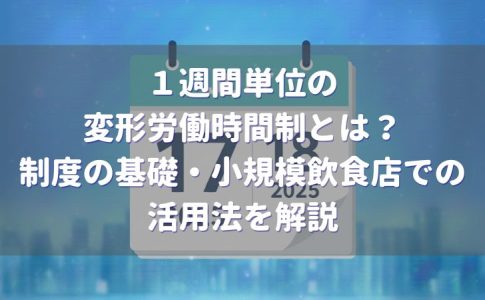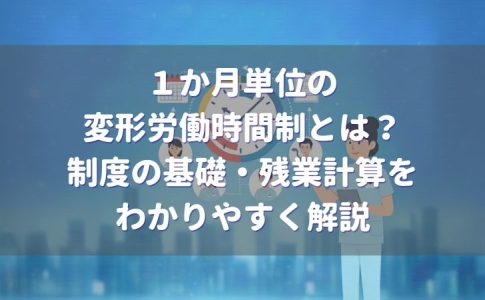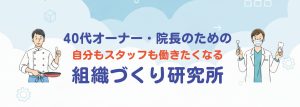神戸市の歯科医院の院長先生、飲食店や美容室を経営されているオーナーさま。
「スタッフの労働時間管理、これで合ってる?」
「有給休暇はいつから何日付与すればいいの?」
「産休・育休の制度がよくわからない…」
このような勤怠管理に関する疑問をお持ちではありませんか?
そこでこの記事では、社労士×生成AI活用アドバイザーの視点から、小規模事業所の経営者が押さえるべき労働時間・休日・休暇の基礎知識を詳しく解説します。
この記事でわかること
- 法定労働時間と休憩時間の正しいルール
- 休日の種類と付与義務
- 有給休暇の付与日数と取得義務
- 産休・育休の基本的な仕組み
目次
労働時間の基礎知識
法定労働時間とは?
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことです。
具体的には以下の通りです。
- 1日8時間以内
- 1週40時間以内
これは正社員だけでなく、パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。
原則、これを超える所定労働時間の設定はできませんが、変形労働時間制を活用することで、1日9時間や、1週48時間といった設定も可能になります。
歯科医院・飲食店・美容室は、特例措置対象事業場の対象業種に含まれているため、事業場の人数が10人未満の場合は、1週44時間以内が法定労働時間となります。
時間外労働(残業)について
法定労働時間を超えて働かせる場合には、36協定(サブロク協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
36協定を締結せずに残業させた場合、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、36協定を締結した場合でも、時間外労働には上限があります。
- 原則:月45時間、年360時間以内
- 特別条項付き:年720時間以内、月100時間未満(複数月平均80時間以内)
36協定を締結せずに残業をさせたとして、書類送検をされた飲食店もあります。
休憩時間のルール
労働時間に応じて、以下の休憩時間を与える必要があります。
| 労働時間数 | 休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 休憩なしでも可 |
| 6時間超~8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間超 | 60分以上 |
もし、1日の所定労働時間が8時間で、休憩45分の設定をしていて残業が発生した場合には、15分の休憩を追加で与える必要があります。
休憩時間は労働時間の途中に与え、労働者が自由に利用できることが原則です。
「電話番をしながら休憩」や「お客様がいらしたら対応する休憩」は、労働から完全に解放されていないため、休憩時間として認められません。
休憩中でも電話が鳴ったら出るというのは、”当たり前”になっていることが多いので、特に注意が必要なポイントです。
社労士が教える労働時間管理のポイント
- タイムカードやICカード、クラウド勤怠管理システムなどで客観的に記録する
- シフト制の場合も、実際の労働時間を正確に把握する
- 開店前の準備時間や閉店後の片付け時間も労働時間に含まれる
- 固定残業手当を支払っている場合でも、残業時間は正確に把握する
固定残業手当を導入されている場合、残業時間の把握をしていないというケースを目にすることがよくあります。
固定残業手当を支払っていても、実際の残業手当の金額が固定残業手当の金額を超えた場合は、その差額を支給が必要となりますので、正確な残業時間の把握が不可欠です。
休日の基礎知識
法定休日とは?
労働基準法では、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
この法律で定められた休日を「法定休日」といいます。
法定休日と法定外休日の違い
多くの企業では週2日の休日を設定していますが、この2日の扱いは異なります。
- 法定休日:労働基準法で義務付けられた休日(週1日または4週4日)
- 法定外休日:企業が独自に設定した休日
この区別が重要なのは、休日労働の割増賃金率が異なるためです。
- 法定休日の労働:35%以上の割増賃金
- 法定外休日の労働:通常の時間外労働(残業)として25%以上の割増賃金(週40時間を超える場合)
週休2日で、そのうちどちらかの休日に勤務した場合は、原則、時間外労働(残業)となるため、25%以上の割増が必要となります。
⇒休日出勤=35%とされているケースがありますが、法律上は25%でも問題ありません。
休日労働をさせる場合の注意点
法定休日に労働させる場合も、36協定の締結と届出が必要です。
また、2025年のガイドラインでは「勤務間インターバル制度」の導入推進が強調されており、休日出勤が連続する場合は健康確保の観点からも注意が必要です。
振替休日と代休
休日に労働させた場合に、「振替休日」と「代休」という2つの方法で休日を付与することがありますが、この2つは全く異なる制度です。
振替休日とは
あらかじめ休日と労働日を入れ替える制度です。
- タイミング:休日労働をさせる前日までに代わりの休日を指定
- 割増賃金:原則として休日労働の割増賃金(35%)は不要
※振替によって、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、25%の割増賃金が必要 - 要件:就業規則に規定が必要、事前に振替日を特定する
※36協定を締結、届け出をしておくほうが良い
例:「日曜日にイベントがあるので出勤してください。代わりに木曜日を休みにします」と事前に決める
代休とは
休日労働をした後に、その代償として別の日を休みにする制度です。
- タイミング:休日労働の後に代わりの休日を取得
- 割増賃金:法定休日労働の場合、35%の割増賃金が必要
- 要件:36協定が必要
※割増賃金を支払うため、法律上は代休を与える義務はない
例:「急なトラブルで日曜日に出勤てくれたので。今度の水曜日は休んでください」と実際に勤務をした後に、休日を与える
振替休日・代休の重要な注意点
前述のとおり、振替休日の場合でも、週をまたいで振替を行い週40時間を超えた場合は、時間外労働の割増賃金(25%)が必要になります。
また、未消化の振替休日や代休が累積すると、賃金の全額払いの原則に違反する可能性があるため、速やかな取得を促すことが重要です。
社労士が教える休日管理のポイント
- 就業規則で法定休日を明確に定める(例:「日曜日を法定休日とする」)
- シフト制の場合、確実に週1日または4週4日の休日を確保する
- 振替休日を活用する場合は、必ず事前に振替日を特定し、本人に通知する
- 振替休日・代休の未消化が累積しないよう、取得状況を管理する
- 連続勤務日数が長くならないよう配慮する
- スタッフの健康管理のため、適切な休日取得を促進する
有給休暇の基礎知識
有給休暇の付与要件
年次有給休暇は、以下の2つの要件を満たすすべての労働者に付与する義務があります。
- 雇い入れから6か月以上継続勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
正社員だけでなく、正社員よも勤務時間や勤務日数が少ないパート・アルバイトにも付与義務があります。
有給休暇の付与日数
正社員などフルタイム労働者の場合
| 勤続年数(入社日~) | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月 | 20日 |
| 以降1年ごと | 20日 |
パート・アルバイトの場合(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合)
週の所定労働日数や年間の所定労働日数に応じて、以下の図のとおり比例付与されます。
| 週所定 労働日数 | 年間所定 労働日数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169日〜 216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜 168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜 120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
原則、週の所定労働日数によって判断しますが、週以外の期間で所定労働日数が決められている場合は、年間の所定労働日数によって判断します。
表の見方(例)
- 週2日勤務の場合:6か月で3日、1年6か月で4日、3年6か月で5日、6年6か月以上で7日
- 週3日勤務の場合:6か月で5日、1年6か月で6日、3年6か月で8日、5年6か月で10日(年5日取得義務の対象)、6年6か月以上で11日
- 週4日勤務の場合:6か月で7日、3年6か月で10日(年5日取得義務の対象)、6年6か月以上で15日
年5日の取得義務
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日を取得させることが義務付けられています。
この義務を果たさなかった場合、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
有給休暇の繰越と時効
有給休暇の時効は2年です。取得しなかった有給休暇は翌年に繰り越されますが、付与日から2年で消滅します。
つまり、最大で40日(20日×2年分)まで保有できますが、3年目には古い分から消滅していきます。
社労士が教える有給休暇管理のポイント
- 「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務がある
- 労働者が自ら取得する日数が5日に満たない場合、会社が時季指定する
- 計画的付与制度を活用すると、取得促進と業務の平準化が図れる
- 有給休暇の買取りは原則禁止(退職時の未消化分や時効により消滅した分は例外)
産休・育休の基礎知識
産前産後休業(産休)とは?
産休は労働基準法で定められた、妊娠・出産する女性労働者のための休業制度です。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人が請求すれば取得できる
- 産後休業:出産の翌日から8週間は就業させてはならない(産後6週間経過後、本人が希望し医師が認めた場合は就業可)
産休は、正社員・パート・アルバイト・派遣社員など、すべての女性労働者が対象です。
育児休業(育休)とは?
育休は育児・介護休業法で定められた、男女問わず取得できる休業制度です。
- 対象:原則1歳未満の子を養育する労働者(保育所に入所できない等の場合は最長2歳まで延長可)
- 取得回数:1人の子について、原則2回まで分割取得可能
- 産後パパ育休:子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能(2回まで分割可)
ただし、以下の労働者は対象外となる場合があります。
- 雇用期間が1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
産休・育休中の賃金と社会保険
賃金
産休・育休中の賃金支払いは、労働基準法上の義務ではありません。多くの企業では無給としています。
ただし、以下の給付金制度があります。
- 出産手当金:健康保険から支給(産休中)
- 育児休業給付金:雇用保険から支給(育休中、休業開始時賃金の67%(6か月経過後は50%))
- 出生時育児休業給付金:産後パパ育休中に支給
- 出生後休業支援給付金:2025年4月から新設
社会保険料
産休・育休中は、健康保険料・厚生年金保険料が事業主負担分・本人負担分ともに免除されます。
2025年の法改正ポイント
2025年4月と10月に育児・介護休業法が改正されています。
- 短時間勤務制度の対象拡大:3歳以上小学校就学前まで拡大
- テレワークの努力義務化:柔軟な働き方の選択肢として
- 個別の意向聴取義務:従業員の両立支援ニーズを把握し配慮
- 育児時短就業給付金:2歳未満の子を持ち時短勤務する場合に支給
社労士が教える産休・育休対応のポイント
- 妊娠の報告を受けたら、制度について書面で説明し、取得意向を確認する
- 産休・育休を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されている
- 育休中も出勤率の算定では「出勤したもの」として扱う(有給休暇付与に影響)
- 復帰後の配置や業務内容について、事前に本人と面談して調整する
- 就業規則に産休・育休に関する規定を必ず記載する
勤怠管理でよくある質問
まとめ:労働時間・休日・休暇の適切な管理で働きやすい職場へ
本記事では、労働時間・休日・休暇の基礎知識について詳しく解説しました。
重要ポイント
- 法定労働時間は1日8時間・週40時間以内、休憩は労働時間に応じて45分または1時間以上
- 休日は週1日または4週4日以上の確保が義務
- 有給休暇は雇入れ6か月後から付与、年10日以上付与される労働者には年5日取得させる義務
- 産休は女性労働者の権利、育休は男女問わず取得可能
- 2025年4月から育児・介護休業法が改正され、柔軟な働き方が促進されている
神戸市の歯科医院、飲食店、美容室の皆様が、これらのルールを正しく理解し、自分もスタッフも働きたくなる組織づくりを実現していただければ幸いです。
🎯 労務管理でお困りの方へ
無料相談実施中!
✅ 勤怠管理の課題が30分でわかる
✅ 就業規則の作成・見直しのアドバイス
✅ AI活用による効率化提案
【神戸市の小規模事業所様向け特別サポート】
初回相談無料
当事務所では、神戸市の小規模事業所の皆様に特化した労務管理サポートを行っています。労働時間管理、有給休暇の取得促進、産休・育休への対応など、お気軽にご相談ください。
また、生成AIを活用した効率的な労務管理の方法もご提案しています。