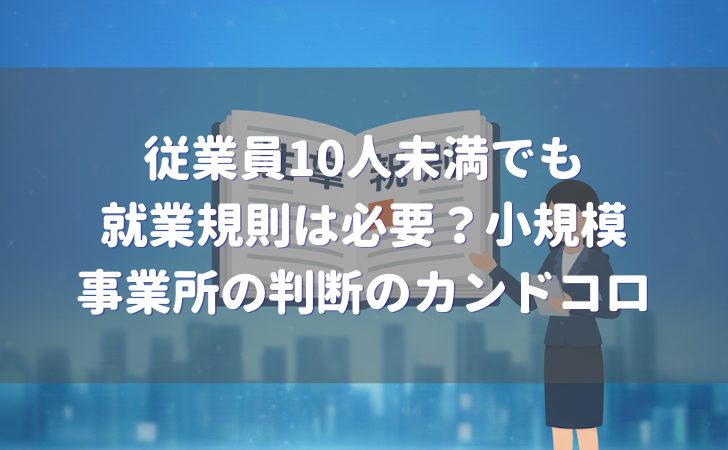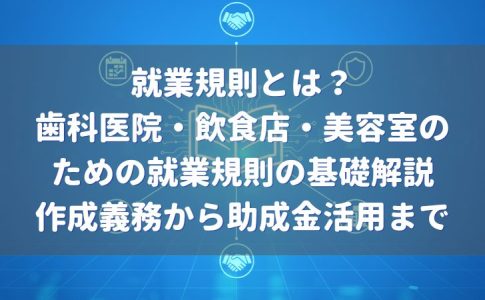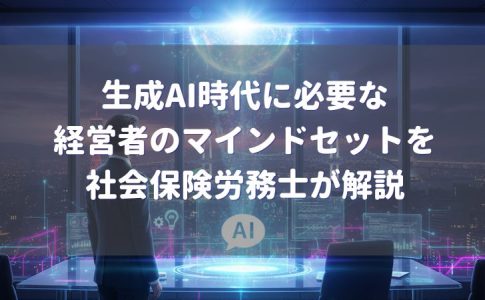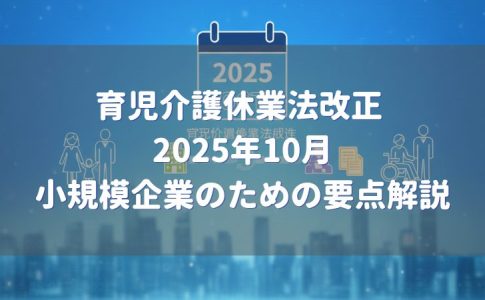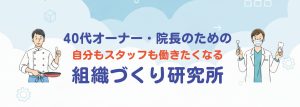従業員10人未満の事業所では、就業規則の作成義務はありません。しかし、作成しないことで生じるリスクをご存知でしょうか?
実際に、神戸市内の小規模飲食店では、就業規則がなかったために従業員とのトラブルが発生し、解決に多額の費用と時間を要した事例があります。
一方で、5人規模の美容室が就業規則を整備したことで、スタッフの定着率が向上したケースも存在します。
そこでこの記事では、社会保険労務士&生成AI活用アドバイザーの視点から、法的義務の有無だけでなく、就業規則を作成すべきかの判断基準を解説します。
さらに、AIツールを活用した効率的な作成方法もご紹介します。
目次
就業規則の法的義務を正しく理解する
10人未満は作成義務なし、でも…
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業所には就業規則の作成・届出義務があります。つまり、従業員9人以下の事業所には法的義務はありません。
ただし、「義務がない=不要」ではない点に注意が必要です。なぜなら、就業規則は労使トラブルを予防し、事業運営を円滑にする重要なツールだからです。
神戸市内に限らず、従業員5〜9人の段階で就業規則を作成する企業が増えています。特に、飲食店や美容室、歯科医院など人材の定着が課題となる業種では、早期の整備が効果的です。
作成義務がない事業所で起こりやすいトラブル
就業規則がない小規模事業所では、以下のようなトラブルが発生しがちです。
- 残業代の計算方法が不明確で、退職時に未払い請求される
- 有給休暇の取得ルールが曖昧で、スタッフ間で不公平感が生まれる
- 服装や接客態度の基準がなく、注意しても改善されない
- 退職の申し出時期が口約束だけで、突然辞められて困る
これらのトラブルは、明文化されたルールがないために発生します。そのため、従業員数が少なくても、基本的なルールを定めておくことが重要です。
実際に、ある飲食店では、退職トラブルから労働審判に発展し、解決までに80万円以上の費用がかかったケースがあります。
小規模事業所が就業規則を作成すべき3つの理由
理由1:労務トラブルの予防と早期解決
就業規則は「会社のルールブック」として機能します。労働条件や服務規律が明文化されていれば、従業員との認識のずれを防げます。
例えば、美容室では遅刻が多いスタッフへの対応に悩むことがあります。しかし、就業規則に遅刻の定義と対応方法が記載されていれば、公平かつ明確に指導できます。
また、トラブルが発生した際も、就業規則があれば解決の根拠となります。そのため、訴訟リスクの軽減にもつながるのです。
就業規則がなくても従業員は法律に守ってもらえますが、相当従業員が悪質なケースを除いては、事業主は就業規則がないと誰も守ってくれません。
理由2:従業員の安心感と定着率向上
明確なルールは、経営者だけでなく従業員にもメリットがあります。なぜなら、労働条件が明示されることで、安心して働ける環境が生まれるからです。
とある歯科医院では、勤務態度不良のスタッフに対して、就業規則を根拠に毅然とした対応を行い、結果として、他のスタッフが「きちんと注意してもらえて良かった」という声が挙がっています。
特に、若い世代の従業員は、曖昧なルールよりも明文化された制度を好む傾向があります。したがって、採用力の強化にもつながります。
理由3:助成金申請の必須要件になる
多くの雇用関係助成金では、就業規則の提出が要件となっています。例えば、キャリアアップ助成金や両立支援等助成金などです。
従業員10人未満でも申請可能な助成金は多数存在します。しかし、就業規則がなければ、せっかくの支援制度を活用できません。
助成金は、従業員数に関係なく受給できるものがほとんどですが、就業規則の整備が前提となるケースが多いため、早めの準備が推奨されます。
神戸市の小規模事業所が活用できる支援制度
就業規則作成サポート in 神戸
神戸市では、小規模事業者向けに様々な労務支援を提供しています。例えば、神戸市産業振興センターでは、専門家による無料相談会を定期開催しています。
また、兵庫県社会保険労務士会でも、中小企業向けの労務相談窓口を設置しています。これらのサービスを活用すれば、コストを抑えて専門的なアドバイスを受けられます。
業種別の特徴と神戸市での実態
飲食店の場合:
神戸市内には約4,500店の飲食店があり、その多くが従業員10人未満です。シフト制や変形労働時間制の導入が多いため、労働時間管理のルール化が重要になります。
美容室の場合:
神戸市の美容室は約1,200店舗。技術者の育成期間が長く、労働条件の明確化が定着率に直結します。特に、歩合給制度や指名料の取り扱いを明記すべきです。
歯科医院の場合:
神戸市内の歯科医院は約800施設。医療従事者特有の労働条件(患者様情報の取り扱い、感染リスクなど)を規定する必要があります。
これらの業種に共通して多いのが、所定労働時間の設定ミスです。知らずしらずのうちに、1日8時間や1週40時間を超えた設定になってしまっています。
適切に就業規則で変形労働時間制を規定するなどの対応が必要です。
AIツールで効率的に就業規則を作成する方法
ChatGPTとNotebookLMの活用術
就業規則の作成は専門知識が必要ですが、AIツールを使えば大幅に効率化できます。具体的には、以下のような活用方法があります。
- ChatGPTの活用例: 業種別の就業規則サンプルの生成、法改正情報の要約と反映箇所の提案、従業員への説明文書の作成
- NotebookLMの活用例: 既存の社内ルールや口頭約束の整理、他社事例や行政資料の分析、自社に必要な規定項目の抽出、社内ルール専用の問い合わせ窓口としても活用可能
例えば、「飲食店向け就業規則の基本項目を教えて」とChatGPTに質問すれば、業種特性を踏まえた項目リストが得られます。
AI活用時の注意点と専門家確認の重要性
AIツールは便利ですが、生成された内容をそのまま使用するのは危険です。なぜなら、法的に不適切な表現や、自社の実態に合わない内容が含まれる可能性があるからです。
- 最新の労働法令に準拠しているか
- 自社の実態と矛盾していないか
- 従業員に不利益な変更になっていないか
- 業種特有の規制に対応しているか
したがって、AIで作成した就業規則案は、必ず社会保険労務士などの専門家によるチェックを受けることを推奨します。
就業規則作成の具体的ステップ
1.まず最低限必要な項目から始める
いきなり完璧な就業規則を作ろうとすると挫折します。そこで、まずは労働基準法で必須とされる絶対的記載事項から着手しましょう。
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期
- 退職に関する事項(解雇事由含む)
これら3項目だけでも明文化すれば、主要なトラブルの多くを予防できます。その後、業務の実態に応じて、服務規律や懲戒規定などを追加していけば良いのです。
2.作成後の運用と定期的な見直し
就業規則は作成して終わりではありません。実際に、法改正や事業内容の変化に応じて、定期的な見直しが必要です。
- 法改正があったとき(年1回は確認)
- 従業員数が10人に達したとき
- 新しい働き方を導入するとき(短時間勤務や週休3日など)
- トラブルが発生したとき
定期的に就業規則の見直しを実施して、それをアナウンスしている事業所では、常に実態に即したルール運用ができており、スタッフからの信頼も厚いです。
また、AIツールを使えば、法改正情報の確認や規定の更新案作成も効率化できます。そのため、定期見直しの負担も大幅に軽減されます。
就業規則作成についてよくある質問
今後のアクション
今すぐできる第一歩
まずは、現在の労働条件を紙に書き出してみましょう。始業・終業時刻、休日、給与の支払方法など、基本的な項目だけでも構いません。
次に、無料のAIツール(ChatGPTなど)で「○○業の就業規則サンプル」と検索し、自社に必要な項目を確認してみましょう。これだけでも、就業規則作成の具体的なイメージが湧いてきます。
専門家への相談のタイミング
「AIで作成した内容が法的に問題ないか確認したい」
「業種特有の規定をどう書けばいいか分からない」
「助成金申請を見据えた就業規則を作りたい」
「従業員への説明方法を相談したい」
こうした疑問が出てきたときが、専門家へ相談するタイミングです。
神戸市での就業規則作成サポート
当事務所では、神戸市の小規模事業所向けに、誰が読んでも理解できる「わかりやすい就業規則」作成サポートを提供しています。
初回相談(30分)は無料ですので、「まずは何から始めればいいか知りたい」という段階でもお気軽にお問い合わせください。
飲食店、美容室、歯科医院など、業種別の実践的なアドバイスをご提供します。
「自分もスタッフも働きたくなる組織」の基盤づくりを、一緒に始めませんか?