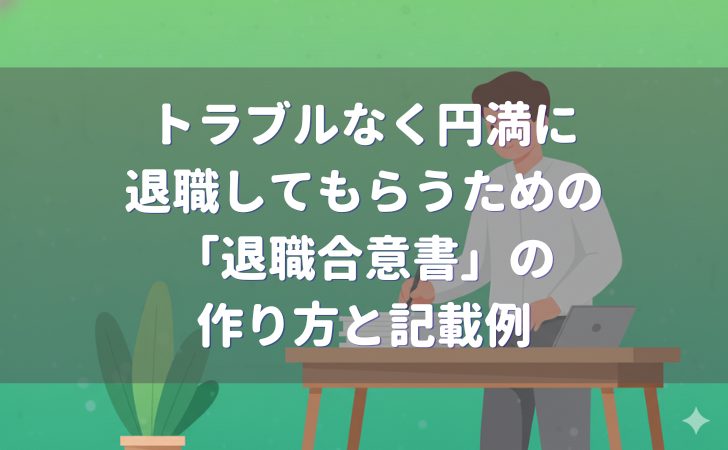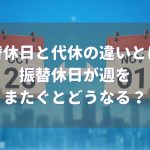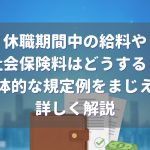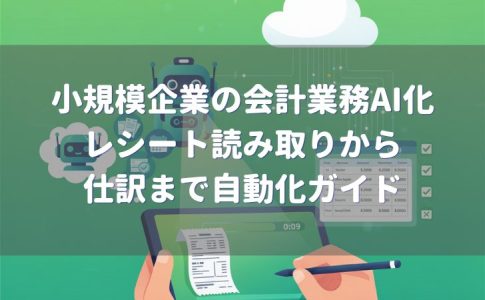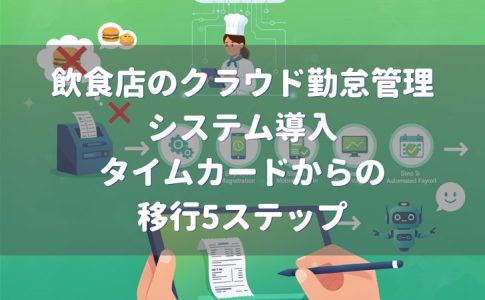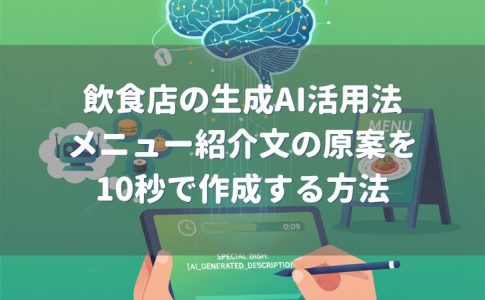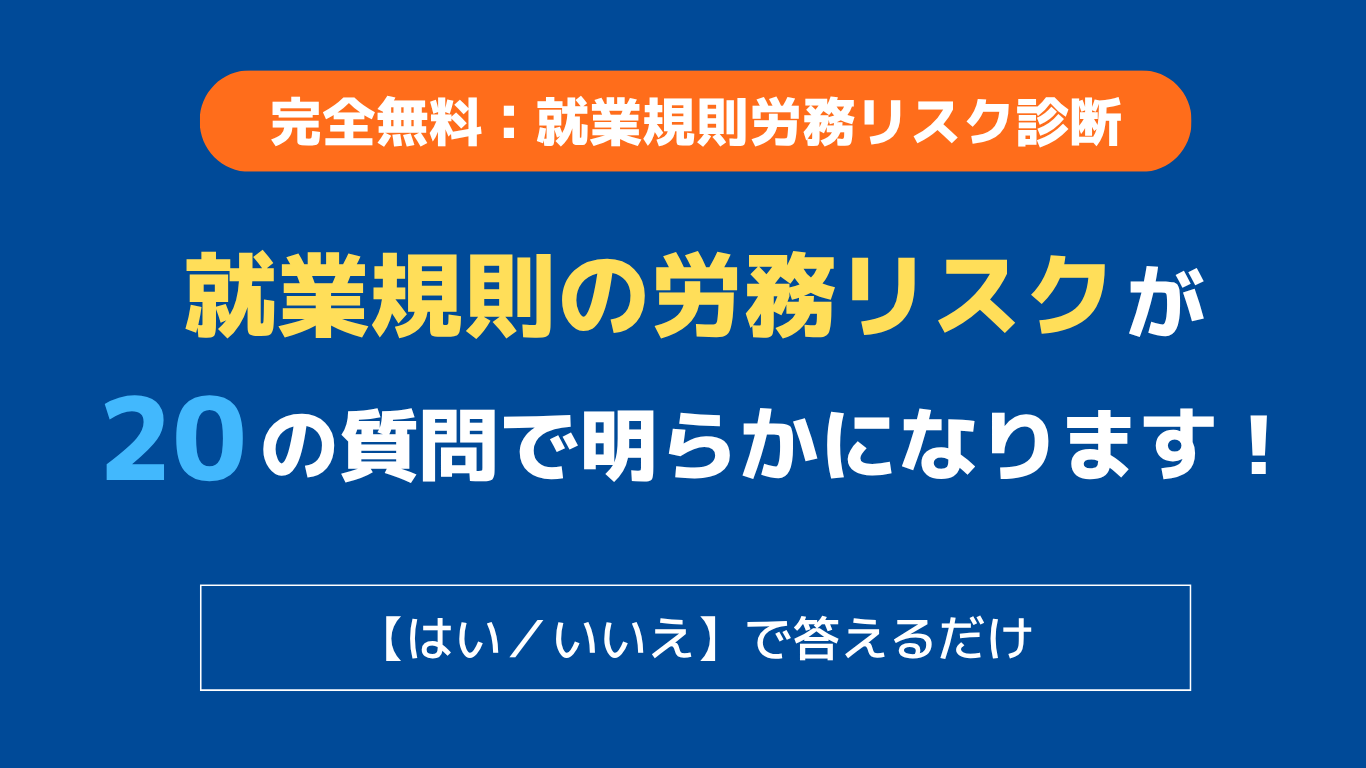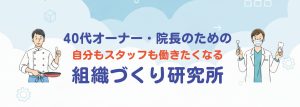神戸市で飲食店、美容室、歯科医院を経営されているオーナー、院長先生。
少し揉めたり、感情の行き違いがあったスタッフさんの退職時に、何かしらのトラブルが起きてしまうのではないかと不安に感じていませんか?
退職後に未払い残業代を請求されたり、顧客情報が流出したりといった問題が、小規模事業所では大きなダメージになることがあります。
そんな時に役立つのが「退職合意書」です。
そこでこの記事では、社労士×生成AI活用アドバイザーの視点から、トラブルなく円満に退職してもらうための「退職合意書」の作り方と記載例を詳しく解説します。
この記事でわかること
- 退職合意書の基本的な作り方と必須記載事項
- 小規模事業所向けの具体的な記載例とポイント
- トラブルを防ぐための注意点と対応方法
目次
退職合意書とは?基礎知識を確認
退職合意書の定義
退職合意書とは、店舗・医院とスタッフが退職に関する条件や約束事項について合意した内容を記載した書面です。
退職届が従業員からの一方的な意思表示であるのに対し、退職合意書は双方の署名・押印により、退職に関して合意があったことを証明する重要な文書となります。
解雇については、事業主側からの一方的な意思表示です。
そのため、当事務所では、解雇をする前に退職勧奨を行い、退職合意書を作成することをおすすめしています。
神戸市の小規模事業所における必要性
神戸市内の飲食店、美容室、歯科医院などの小規模事業所では、スタッフ一人ひとりの役割が大きく、急な退職や退職後のトラブルが事業運営に直結します。
退職合意書を作成することで、退職条件を明確にし、双方が納得した形で円満退職を実現することができます。
退職合意書が必要な3つの理由
退職合意書を作成する主な理由は次の3つです。
1.合意のうえでの退職である証明
合意退職であることを明確にし、後日「解雇された」と主張されるリスクを回避できます。
2.残業代などの金銭に関する債権債務の生産
残業代(未払い賃金)や退職金などの金銭関係を清算し、退職後の請求トラブルを防止できます。
3.情報漏洩のリスク軽減
顧客情報や営業秘密の保護について合意書に明記し、約束させることで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
退職合意書の具体的な作り方【ステップ解説】
準備するもの
退職合意書を作成する前に、以下のものを準備しましょう。
- 雇用契約書・就業規則
- 退職理由と退職日の確認メモ
- 退職金・未払い賃金の計算資料
- 事業主(法人の場合は代表者印・理事長印)の印鑑とスタッフの印鑑
ステップ1: 退職の合意内容を話し合う
まず、スタッフと退職について話し合いを行います。
退職日、退職理由、有給休暇の消化、引き継ぎ期間などについて、双方が納得できる内容を決定します。
この段階で無理に合意を迫ると、後日「退職強要があった」と主張されるリスクがあるため、スタッフの自由な意思を尊重することが重要です。
退職勧奨を行う場合は、面談の回数や時間、参加人数に配慮し、録音されていることを想定して言動に注意しましょう。
ステップ2: 必須条項を盛り込んだ書面を作成する
話し合いで合意した内容をもとに、退職合意書を作成します。以下の条項は必ず記載しましょう。
1. 退職日と退職理由
「甲(会社)と乙(従業員)は、乙が令和○年○月○日付で【自己都合・事業主都合】により退職することを合意した。」
2. 金銭の支払い条件
退職金や未払い賃金がある場合は、金額、支払日、支払方法を明記します。
3. 秘密保持義務
在職中に知り得た顧客情報や営業秘密を第三者に開示しないことを約束させます。
ただし、あまりに範囲が広すぎると無効とされる可能性があるため、具体的に特定することが大切です。
4. 清算条項
「甲及び乙は、甲乙間に、本合意書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認する。」
この清算条項により、退職後の追加請求を防ぐことができます。
ステップ3: 内容を丁寧に説明し、署名・押印をもらう
作成した退職合意書の内容を、スタッフに丁寧に説明します。
専門用語や分かりにくい表現がある場合は、かみ砕いて説明し、スタッフが内容を十分に理解した上で署名・押印をもらうことが重要です。
急がせたり、内容の説明を省いたりすると、後日「自由な意思でサインしていない」として無効を主張される可能性があります。
ステップ4: 双方が原本を保管する
退職合意書は2通作成し、店舗・医院とスタッフがそれぞれ1通ずつ保管します。
法定の保存期間はありませんが、将来のトラブルに備えて長期間保存しておくことをお勧めします。
小規模事業所向け退職合意書の記載例
基本的な記載例(飲食店・美容室・歯科医院共通)
以下は、小規模事業所で使いやすい退職合意書の基本例です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
退職合意書
○○○○(以下「甲」という。)と従業員△△△△(以下「乙」という。)は、甲乙間の雇用契約の解約に関し、次のとおり合意した。
第1条(退職)
甲と乙は、乙が甲を令和○年○月○日付で自己都合により退職することを合意した。
第2条(退職金等の支払い)
甲は、乙に対し、退職金として金○○円を、令和○年○月○日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第3条(有給休暇の取扱い)
乙の残存する年次有給休暇○日については、退職日までに消化するものとする。
第4条(引き継ぎ)
乙は、退職日までに、担当業務の引き継ぎを完了するものとする。
第5条(秘密保持)
乙は、在職中に知り得た甲の顧客情報、技術情報、営業秘密その他の機密情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。
第6条(口外禁止・誹謗中傷の禁止)
甲及び乙は、本合意書の内容及び合意に至った経緯について、第三者に開示、漏洩しない。甲及び乙は、互いに相手を誹謗中傷する行為をしない。
第7条(清算条項)
甲及び乙は、甲乙間に、本合意書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認する。
本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
甲:住所・氏名・印
乙:住所・氏名・印
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
業種別の追加条項例
飲食店の場合
「乙は、退職後○年間、甲の店舗から半径○km以内において、同種の飲食業を営んではならない。」
※競業避止義務は、期間や範囲が過度に広いと無効となる可能性があるため、合理的な範囲に限定することが重要です。
美容室の場合
「乙は、甲の顧客に対し、退職後に個別に連絡を取り、自己の営業する店舗への来店を勧誘してはならない。」
歯科医院の場合
「乙は、患者のカルテ情報、診療記録その他の個人情報を、いかなる方法によっても第三者に開示、漏洩してはならない。」
トラブルを防ぐための注意点
よくあるトラブル事例
問題1: 「退職強要があった」と主張される
退職合意書にサインをもらっていても、後日「無理やりサインさせられた」と主張されるケースがあります。
解決策: 面談時の記録を残し、スタッフの自由な意思でサインしたことを証明できるようにしておきましょう。面談は複数回に分け、考える時間を与えることも有効です。
問題2: 清算条項があるのに未払い残業代を請求される
退職合意書に清算条項を設けていても、合意書作成時点でスタッフが認識していなかった未払い残業代については、請求される可能性があります。
解決策: 未払い残業代の有無を事前に確認し、ある場合は清算条項に明記するか、別途支払いを行いましょう。
問題3: 退職合意書の作成を拒否される
スタッフが退職合意書へのサインを拒否するケースもあります。
解決策: 無理に説得せず、拒否された場合は専門家に相談しましょう。強要してサインさせても、後で無効とされるリスクがあります。
無効とされやすい条項の例
以下のような条項は、公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。
- 過度に広範囲・長期間の競業避止義務
- あまりに高額な違約金の定め
- 秘密保持義務の対象が「在職中に知り得た一切の情報」など曖昧すぎる規定
これらの条項を設ける場合は、合理的な範囲に限定することが重要です。
【目安】
範囲:店舗から半径1キロ~2キロ以内
期間:1年以内
違約金:○○万円ではなく、「実際に生じた損害を賠償」
秘密保持の対象:顧客の氏名・連絡先などと列挙
確認方法:退職合意書が有効に成立しているかチェック
以下のチェックリストで、退職合意書が有効に成立しているか確認しましょう。
社労士が教える退職合意書作成の労務管理ポイント
法的要件と実践のバランス
退職合意書は法律で作成が義務付けられているものではありませんが、適切に作成することで大きなリスク回避効果があります。
特に小規模事業所では、弁護士に依頼するコストを抑えながらも、最低限の法的保護を確保することが重要です。
基本的な条項を押さえた上で、実情に合わせてカスタマイズしていくことをお勧めします。
小規模事業所特有の注意点
従業員が20名以下の小規模事業所では、以下の点に特に注意が必要です。
- 退職後も地域内で顔を合わせる可能性が高いため、円満退職を最優先する
- 少人数体制のため、引き継ぎ期間を十分に確保する
- SNSでの誹謗中傷が事業に与える影響が大きいため、口外禁止条項を必ず設ける
トラブル予防のための事前対策
退職時のトラブルを予防するためには、日頃から以下の対策を講じておくことが重要です。
- 就業規則に退職手続きの流れを明記しておく
- 雇用契約書に秘密保持義務を規定しておく
- 労働時間を適切に管理し、未払い残業代が発生しないようにする
- 定期的に面談を行い、不満や悩みを早期に把握する
退職合意書についてよくある質問
まとめ:退職合意書で働きたくなる組織へ
本記事では、トラブルなく円満に退職してもらうための「退職合意書」の作り方と記載例について詳しく解説しました。
重要ポイント
- 退職合意書は双方の合意を明確にし、退職後のトラブルを防ぐ重要な書面
- 退職日、金銭関係、秘密保持、清算条項は必ず記載する
- スタッフの自由な意思を尊重し、内容を丁寧に説明することが大切
神戸市の小規模事業所の皆様が、自分もスタッフも働きたくなる組織づくりを実現するため、適切な退職合意書の作成を通じて、円満な退職をサポートします。
🎯 さらなる組織改善をお考えの方へ
無料相談実施中!
✅ 退職合意書の作成サポート
✅ 労務管理の課題が30分でわかる
✅ AI活用による効率化提案
【期間限定】神戸市の小規模事業所様向け特別サポート
初回相談無料
退職合意書の作成でお困りの方、労務管理でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。