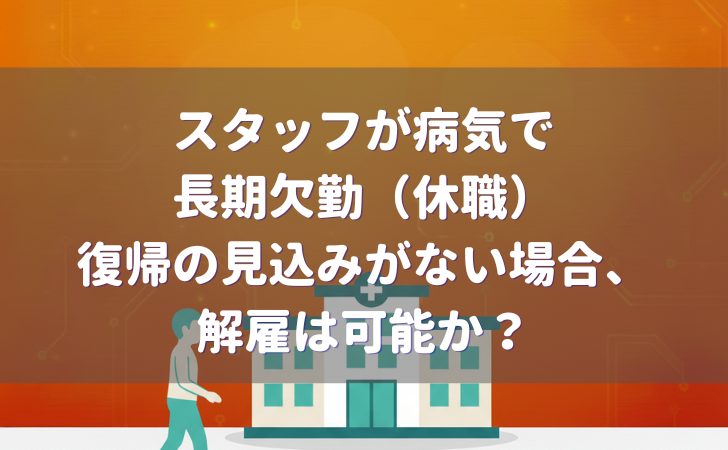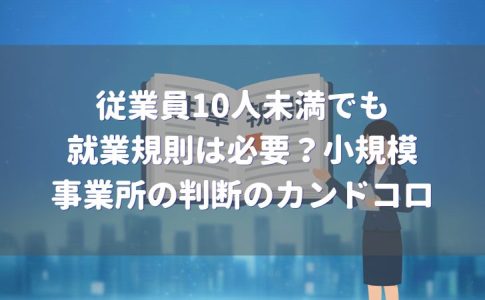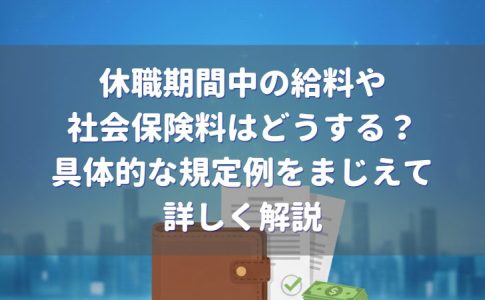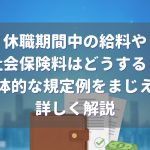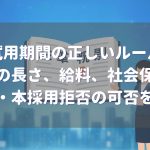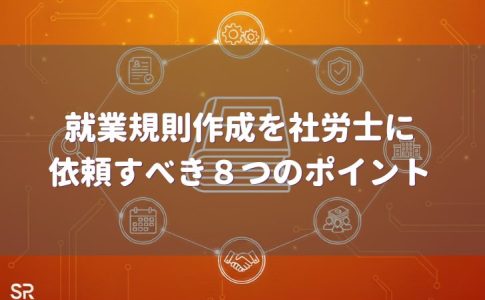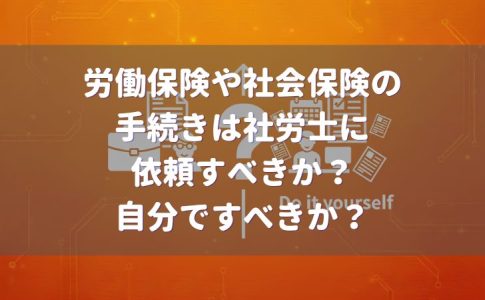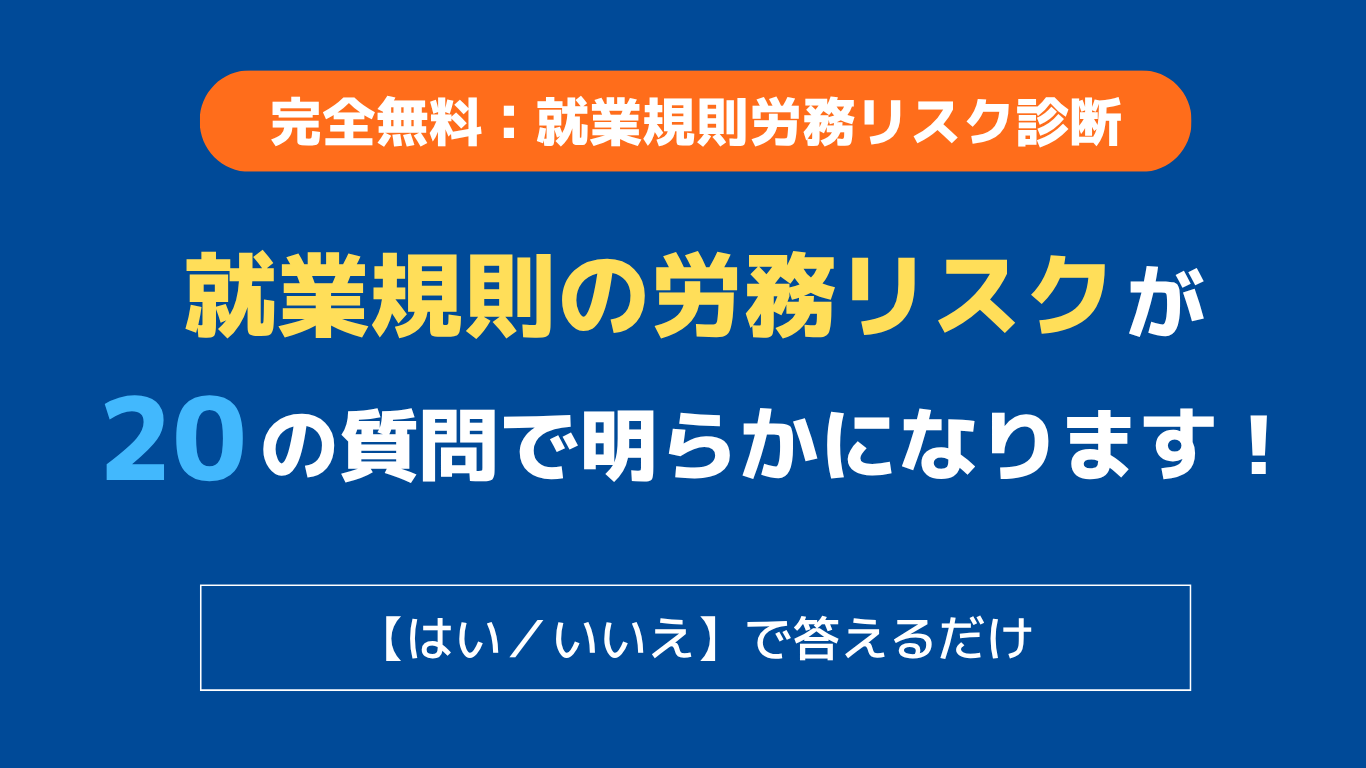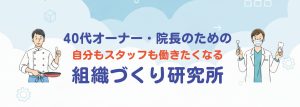神戸市で飲食店、美容室、歯科医院を経営されているオーナー、院長先生。
スタッフが病気で長期欠勤し、復帰の見込みが立たない状況でお困りではありませんか?
「人手不足なのに、いつまで待てば良いのか…」
「解雇できるのか、それとも待つしかないのか…」
小規模事業所では、一人のスタッフが欠けるだけで業務に大きな支障をきたします。しかし、病気を理由とする解雇は慎重な判断が必要です。
そこでこの記事では、社労士×生成AI活用アドバイザーの視点から、病気による長期欠勤のスタッフへの対応について、法的な観点と実務上のポイントを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 病気を理由とする解雇が可能な条件
- 業務上の病気と私傷病の違いと対応の差
- 休職制度の正しい運用方法と重要判例
- 解雇トラブルを避けるための具体的な手順
目次
病気を理由とする解雇の基本ルール
病気を理由とした解雇は可能なのか?
結論から言えば、病気を理由とした解雇は条件次第で可能ですが、簡単には認められません。
労働契約法第16条では、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされています。これを「解雇権濫用法理」といいます。
つまり、病気で働けないからといって、すぐに解雇できるわけではなく、正当な理由と適切な手続きが必要なのです。
最も重要な区別:業務上の病気か私傷病か
病気による解雇を考える際、最も重要なのは、その病気が「業務上」のものか「私傷病」かの区別です。
業務上の病気・怪我の場合
労働基準法第19条により、業務上の負傷や疾病で療養中の期間とその後30日間は、原則として解雇が禁止されています。
例外として、療養開始後3年を経過しても治らない場合で、労災保険の傷病補償年金を受給している場合などには解雇が可能になります。
私傷病(業務外の病気・怪我)の場合
私傷病の場合は、業務上の病気と異なり、法律による解雇制限はありません。ただし、就業規則の定めに従って対応する必要があります。
重要な注意点: 当初は私傷病と思われていても、後から「業務が原因」と主張されるケースがあります。この判断は慎重に行う必要があります。
近年、メンタル系の疾患について、業務が原因で発症したとして、労災認定されるケースが増えています。
私傷病の場合:休職制度の役割と重要性
休職制度は、解雇を一定期間猶予する制度と言えます。
スタッフが病気になった場合、ただちに解雇するのではなく、休職期間を設けることで回復の機会を与え、雇用を維持することを目的としています。
多くの企業では、次のような休職規定を設けていることが多いです。
一般的な休職規定の例:
「業務外の傷病により、療養のため継続して〇日以上欠勤する場合は、休職を命ずることがある。休職期間は勤続年数に応じて○ヶ月とする。休職期間満了時に病気が治癒していない場合は、退職(または解雇)とする。」
(厚生労働省モデル就業規則の規定を一部変更)
上記のような一般的な規定だけでは、メンタル疾患には対応できないことが多いため、欠勤をしない場合でも、「通常の労務提供ができない」場合なども休職理由として規定することも検討すべきです。
休職期間満了時の判断基準と重要判例
「治癒」「復職可能」の判断基準
休職期間満了時に「復職可能か」を判断する際、重要となるのが「治癒」の定義です。
治癒とは、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態」と定義するのが一般的です。
ただし、「通常の程度」とは、病気になる前と完全に同じレベルまで回復していることを意味するわけではありません。業務に支障のない程度の回復を意味します。
【重要判例】片山組事件(最高裁平成10年4月9日判決)
病気による解雇を判断する上で、必ず知っておくべき重要な最高裁判例があります。
・片山組事件(最高裁平成10年4月9日判決)
(全国公益社団法人全国労働基準関係団体連合会・判例検索より)
事案の概要
建築会社で現場監督をしていた従業員がバセドウ病を発症し、現場作業はできないが事務作業なら可能という診断を受けました。
しかし、会社は自宅治療命令を継続し、賃金を支払いませんでした。従業員は賃金の支払いを求めて訴訟を起こしました。
最高裁の判断
最高裁は、次のように判断しました。
「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合において、特定の業務について労務の提供を十分にできないとしても、その労働者の能力、経験、地位、企業の規模、業種、配置・異動の実情などに照らして、配置される現実的可能性がある他の業務について労務提供ができ、かつ、その提供を申し出ている場合には、債務の本旨に従った履行の提供があるというべきである。」
この判例が示す重要なポイント
この判例は、小規模事業所にとって非常に重要な意味を持ちます。
- ポイント1: 元の仕事ができなくても、他の軽易な仕事ができる場合、配置転換の可能性を検討する必要がある
- ポイント2: 企業規模が大きいほど、配置転換の可能性が広く認められる傾向にある
- ポイント3: 職種や業務内容が労働契約で明確に限定されている場合は、配置転換の義務は軽減される
解雇・退職を検討する際の具体的な手順
STEP1: 就業規則の確認
まず、お店や医院の就業規則を確認しましょう。
確認すべき項目
- 休職制度の有無と休職期間の定め
- 休職期間満了時の扱い(「退職」か「解雇」か)
- 解雇事由として「精神または身体の障害により業務に耐えられないとき」などの規定があるか
就業規則に休職制度がない場合でも、ただちに解雇するのはリスクが高いです。休職制度のように、回復までの猶予期間を設けるなどの配慮が必要です。
STEP2: 休職命令の発令
長期欠勤が続く場合、書面で休職命令を発令します。
休職命令書に記載すべき内容
- 休職事由(医師の診断書に基づく具体的な内容)
- 休職期間の開始日と満了日
- 休職期間中の報告義務
- 復職の条件
口頭ではなく、必ず書面で交付し、記録を残しておくことが重要です。
STEP3: 休職期間中の定期的な状況確認
休職期間中も、定期的にスタッフの状況を確認することが大切です。
確認方法
- 月に1回程度、診断書の提出を求める
- スタッフからの近況報告を受ける
- 必要に応じて、主治医との面談を申し入れる
スタッフには、主治医との面談実現に協力する義務があることを就業規則に明記しておきましょう。
STEP4: 休職期間満了前の復職可否判断
休職期間満了の1〜2ヶ月前から、復職可否の判断プロセスに入ります。
判断に必要な情報収集
- 主治医の診断書: 「復職可能」「軽作業なら可能」「短時間なら可能」などの具体的な意見
- 産業医の意見: 産業医がいる場合は必ず意見を聴取
- 本人の意向: 復職を希望しているか、どの程度の業務なら可能と考えているか
- 配置転換の可能性: 元の仕事ができない場合、他に任せられる仕事があるか
主治医との面談は、本人同席のもとで行うことが望ましいです。裁判になった場合、主治医の意見を聴取したかどうかは非常に重視されます。
配置転換の検討が必要なケース
片山組事件の判例に基づき、以下の場合は配置転換の可能性を検討する必要があります。
- 職種が労働契約で限定されていない場合
- 元の仕事はできないが、軽易な作業なら可能な場合
- 企業規模や業務内容から、配置転換の現実的可能性がある場合
小規模事業所では、配置転換の余地が限られるため、この点は有利に働く可能性があります。ただし、全く検討しないのではなく、可能性を検討したという記録を残すことが重要です。
STEP5: 解雇または退職の手続き
復職不可能と判断した場合、就業規則の定めに従って手続きを進めます。
「退職」扱いの場合
就業規則に「休職期間満了に伴い退職とする」と定められている場合は、自然退職となります。
- 解雇予告や解雇予告手当は不要
- 休職期間満了通知書を交付
- 離職票の離職理由は「自己都合」ではなく「事業主都合」扱いになることが多い
離職票の離職理由が「事業主都合」と判断された場合は、助成金の受給に制限がかかるなどの不利益を被ることがあります。
「解雇」扱いの場合
就業規則に「休職期間満了に伴い解雇する」と定められている場合は、解雇となります。
- 解雇予告: 休職期間満了の30日以上前に解雇予告通知が必要
- 解雇予告手当: 30日前に予告しない場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当が必要
- 解雇理由証明書の交付(従業員から請求があった場合)
休職期間満了の30日前までに解雇予告をしていない場合、解雇予告手当を支払うか、改めて30日後に解雇することになります。
小規模事業所特有の注意点
就業規則がない場合の対応
従業員10名未満の事業所では、就業規則の作成義務はありません。しかし、休職制度や解雇事由を明確にしておくことは非常に重要です。
就業規則がない場合でも、雇用契約書に休職や解雇に関する条項を盛り込むことで、一定の対応が可能になります。
ただし、全スタッフの雇用契約書に休職規定や解雇に関する規定をすべて網羅させるのは、非現実的と言えます。
配置転換の余地がないことの立証
小規模事業所では、「配置転換の余地がほぼない」ことがほとんどです。
ですが、最初から配置転換の余地を検討することを放棄せず、検討を重ねた結果、実現が困難であったという記録を残しましょう。
配置転換が困難であることの記録
- 従業員数と各人の担当業務の一覧
- 休職者の元の業務と、代替可能な業務の検討記録
- 職種が特定されている場合は、その契約内容
これらの記録を残すことで、配置転換を検討したが現実的に困難であったことを示せます。
業種別の特有の課題
飲食店の場合
調理、接客・レジなど、業務が比較的明確に分かれているため、軽作業への配置転換の可能性を検討する必要があります。
ただし、小規模店舗では全員が複数の業務を兼務することが多く、配置転換の余地が限られる点を記録しておきましょう。
美容室の場合
技術職としての性質が強く、職種限定の要素が強い業種です。
スタイリストが手の怪我などで技術業務ができない場合、受付業務などへの配置転換の可能性を検討することになりますが、小規模サロンでは現実的でないことが多いでしょう。
歯科医院の場合
歯科衛生士、歯科助手など、専門性の高い職種です。
感染症リスクのある職場環境のため、免疫力が低下している状態での復職は慎重に判断する必要があります。受付業務への配置転換の可能性はありますが、小規模医院では限定的と言えます。
トラブルを避けるための予防策
記録の重要性
解雇をめぐるトラブルでは、会社側の対応が適切であったことを証明する記録が決定的に重要です。
残すべき記録
- 休職命令書(本人への交付日も記録)
- 定期的に提出された診断書
- 主治医との面談記録(日時、出席者、話し合った内容)
- 産業医の意見書(※)
- 本人との面談記録
- 配置転換可能性の検討記録
- 休職期間満了通知書または解雇予告通知書
※小規模な事業所では、産業医を選任していないことがほとんどです。
その場合でも、事業主側が指定する医師の診断を受けてもらうことも可能ですので、検討材料の一つとすべきです。
主治医との連携の重要性
裁判では、主治医の意見が非常に重視されます。主治医との面談を行わずに復職不可の判断をすると、不当解雇と認定されるリスクが高まります。
主治医面談を実施する際は、本人の同席を得て、以下の点を確認しましょう。
- 現在の病状と今後の見通し
- 元の業務に復帰可能か
- 軽作業なら可能か、その場合どの程度の作業か
- 今後の治療方針と回復の見込み
リハビリ勤務(試し出勤)の活用
復職可能かどうかの判断が難しい場合、リハビリ勤務を実施することで、実際の業務遂行能力を確認できます。
リハビリ勤務の結果、やはり業務遂行が困難であると判断された場合、その記録は復職不可判断の重要な根拠となります。
よくある質問
まとめ:病気による長期欠勤への適切な対応で組織を守る
本記事では、スタッフが病気で長期欠勤し、復帰の見込みがない場合の対応について詳しく解説しました。
重要ポイント
- 病気を理由とする解雇は可能だが、業務上の病気か私傷病かで大きく異なる
- 休職制度は解雇猶予制度であり、適切な運用が重要
- 片山組事件など重要判例に基づき、配置転換の可能性も検討する必要がある
- 主治医の意見聴取と詳細な記録が不当解雇トラブルの予防に不可欠
- 小規模事業所では配置転換の余地が限られることを記録として残す
神戸市の小規模事業所の皆様が、適切な労務管理を通じて、自分もスタッフも働きたくなる組織づくりを実現できることを願っています。
🎯 病気による長期欠勤でお困りの経営者様へ
無料相談実施中!
✅ 休職制度の整備から運用まで完全サポート
✅ 就業規則の見直しと最適化
✅ 解雇トラブル予防のための記録作成支援
【期間限定】神戸市の小規模事業所様向け特別サポート
初回相談無料
病気による長期欠勤への対応は、一歩間違えると大きなトラブルに発展します。専門家のサポートで、法的リスクを最小限に抑えながら、適切な対応を実現しましょう。
お気軽にお問い合わせください。神戸市の小規模事業所の皆様の組織づくりを全力でサポートいたします。