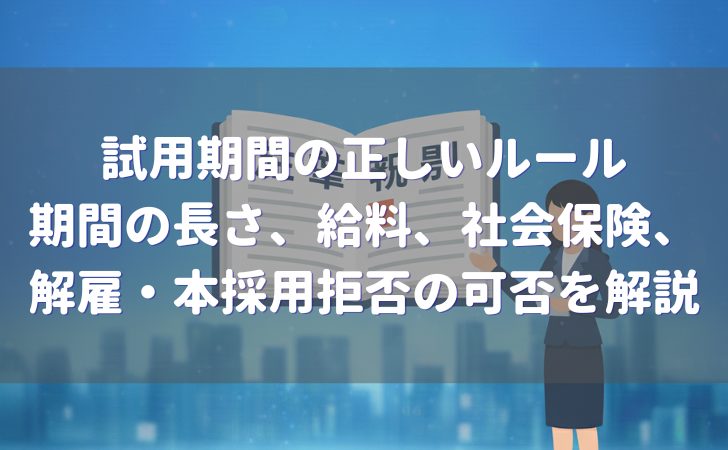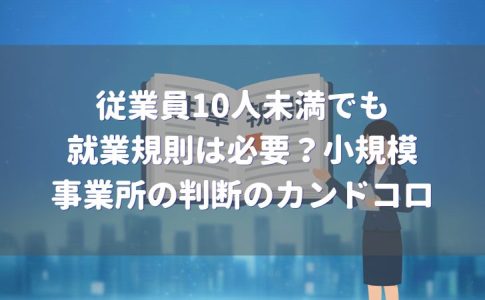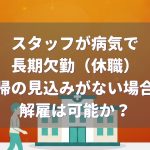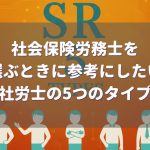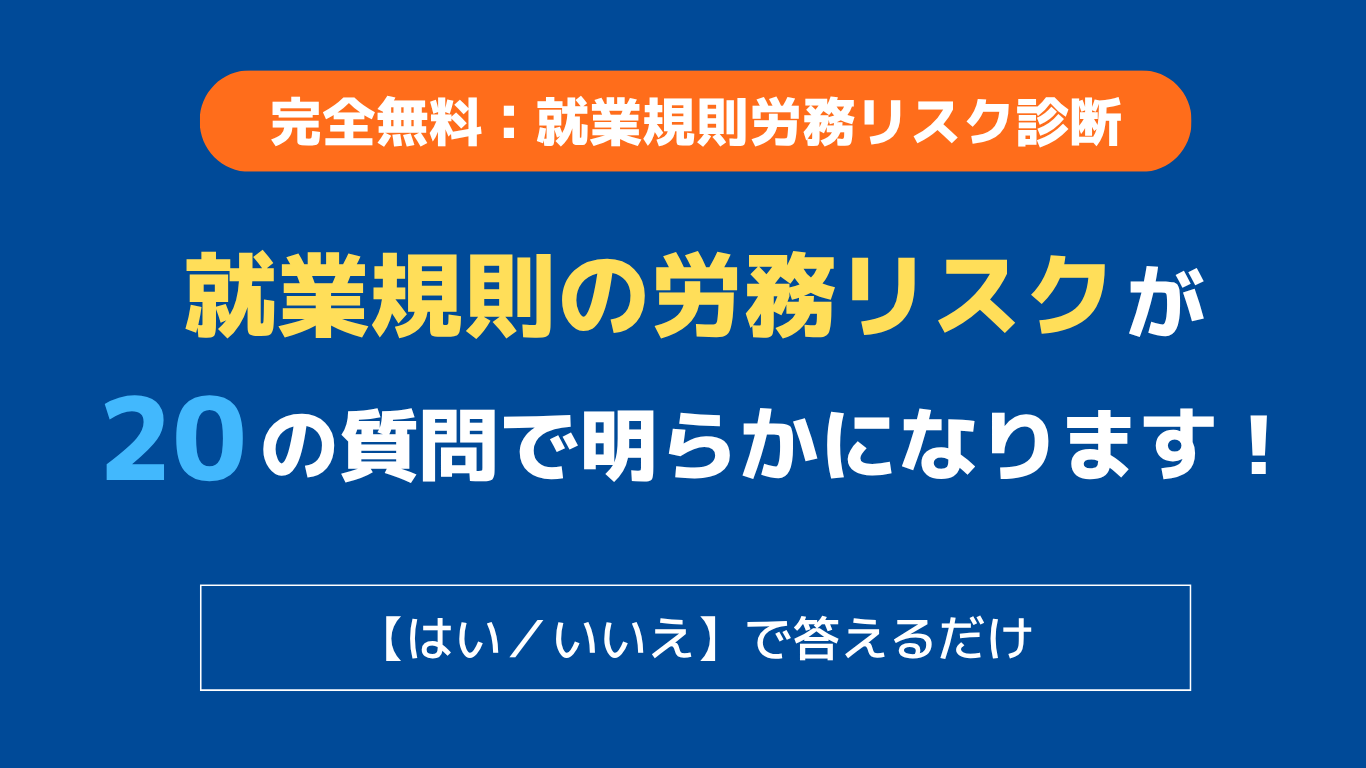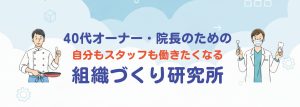神戸市で飲食店や美容室、歯科医院を経営されているオーナー、院長先生。
新しいスタッフを採用する際に、
「試用期間中なら自由に解雇できる」
「試用期間中は社会保険に入れなくても大丈夫」
と考えていませんか?
実は、これらは大きな誤解です。
試用期間にも明確なルールがあり、間違った運用をすると法的トラブルに発展する可能性があります。
そこでこの記事では、社労士の視点から試用期間の正しいルールを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 試用期間の法的な位置づけと適切な期間の長さ
- 試用期間中の給料と社会保険の正しい取り扱い
- 本採用拒否や解雇が認められるケースと注意点
目次
試用期間とは?基礎知識を確認
試用期間の法的な意味
試用期間とは、採用した従業員の適性や能力を実際の業務を通じて見極め、本採用するかどうかを判断するための期間です。
重要なのは、試用期間中であっても正式な労働契約は成立しているという点です。つまり「お試し雇用」ではなく、本採用を前提とした雇用契約なのです。
法律上、試用期間は「解約権留保付き労働契約」と呼ばれます。これは通常の労働契約よりも若干広い範囲で解雇が認められるものの、自由に解雇できるわけではありません。
試用期間に法律上の定めはない
実は、労働基準法には試用期間についての直接的な規定はありません。各企業が就業規則や雇用契約書で独自に設定できます。
ただし、試用期間を設ける場合は、就業規則や雇用契約書に明記する必要があります。口頭での約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。
神戸市の小規模事業所における現状
神戸市内の飲食店や美容室、歯科医院などの小規模事業所では、スタッフの定着率向上が大きな課題となっています。
試用期間を適切に運用することで、採用のミスマッチを防ぎ、お互いが納得した上で長期的な雇用関係を築くことができます。
試用期間の長さはどれくらいが適切か
一般的な試用期間の長さ
多くの企業では、3ヶ月から6ヶ月程度の試用期間を設定しています。
この期間であれば、従業員の勤務態度や適性を十分に判断できると考えられています。
当事務所の関与先さまでは、3ヶ月が最も多い傾向にあります。
関与先様長すぎる試用期間は無効になる
試用期間が1年を超えるような長期間の場合、公序良俗違反(民法第90条)として無効と判断される可能性があります。
裁判例でも、労働者の不安定な地位が長期間続くことは望ましくないとされており、合理的な範囲を超えた試用期間は認められません。
ブラザー工業事件(S59.03.23名古屋地判)
「少なくとも現業従業員の場合、見習社員である期間(最短の者で6~9か月、最長の者12~15か月)中に、その適性を判断できる」
(厚生労働省「確かめよう労働条件:労働条件に関する総合サイト」より)
試用期間の延長は可能か
就業規則に規定があれば、試用期間の延長は可能です。ただし、延長には合理的な理由が必要です。
例えば、試用期間中に病気で休職が多く適性判断が困難だった場合や、改善の可能性があるため猶予を与える場合などが該当します。
当初の試用期間と延長期間を合わせて1年以内であれば、適切な試用期間の長さとして認められる可能性が高いです。
試用期間中の給料はどうなるのか
試用期間中の給与設定
試用期間中の給与は、企業が自由に設定できます。本採用後と同じ給与にすることも、低めに設定することも可能です。
ただし、最低賃金を下回ることは絶対に認められません。最低賃金は必ず確認し、それ以上の給与を支払う必要があります。
残業代は必ず支払う
試用期間中であっても、時間外労働や休日労働があれば、割増賃金(残業代)を支払う義務があります。
「試用期間中だから残業代は払わない」というのは明確な労働基準法違反となります。
試用期間中の社会保険はどうなるのか
試用期間中も社会保険加入は必須
試用期間中であっても、加入要件を満たす従業員は原則として入社日から社会保険に加入させる義務があります。
「まだ本採用ではないから社会保険は不要」という考えは完全な誤解です。試用期間中も正式な労働契約が成立しているため、社会保険加入義務は発生します。
社会保険の種類と加入条件
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。
正社員の場合
試用期間中でも、原則として全ての社会保険に加入する必要があります。
パート・アルバイトの場合
1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば加入対象となります。(社会保険加入対象者が50人未満の事業所の場合)
例外的に加入不要なケース
社会保険への加入が不要となるのは、以下の限定的なケースのみです。
- 契約期間が2ヶ月以内で、延長の見込みがない短期雇用契約の場合
- 日雇いや臨時的な雇用(1ヶ月以内)の場合
重要なのは、試用期間後に本採用を前提としている場合は、試用期間が2ヶ月以内であっても社会保険への加入が必要という点です。
未加入の場合の罰則
社会保険の加入義務を怠った場合、以下のようなペナルティがあります。
- 最大2年間遡って保険料の追徴金が発生
- 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)
- 雇用保険の場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(雇用保険法第83条)
また、日本年金機構の調査で指摘された場合、入社日まで遡って加入日を変更しなければならず、半年や1年分の保険料をまとめて支払うことになる可能性もあります。
試用期間中の解雇・本採用拒否は可能か
「試用期間中は自由に解雇できる」は誤解
これは最も多い誤解の一つです。試用期間中であっても、自由に解雇できるわけではありません。
試用期間中の労働契約は「解約権留保付き労働契約」とされ、通常の解雇よりも若干広い範囲で解雇が認められるものの、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があります(労働契約法第16条)。
本採用拒否が認められるケース
本採用拒否が認められるのは、採用時には知ることができなかった事実が明らかになった場合です。
- 経歴や資格の詐称が発覚した場合
- 勤務態度が著しく不良で、指導しても改善が見られない場合
- 業務遂行能力が明らかに不足しており、今後の改善も期待できない場合
- 協調性がなく、職場の秩序を乱す行為が繰り返される場合
本採用拒否に該当する具体的な理由を就業規則で明示しておくことをおすすめします。
解雇予告は必要か
試用期間中であっても、原則として解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。
ただし、雇入れから14日以内であれば、予告なしで即時解雇が可能です(労働基準法第21条)。
14日を超えている場合は、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
これも誤解が多いのですが、14日以内であれば解雇予告なしで解雇可能というのは、手続き上のことだけであって、解雇をすることに客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があることに変わりはありません。
本採用拒否を行う際の注意点
本採用拒否を検討する場合は、以下の点に注意が必要です。
- 問題点について事前に指導し、改善の機会を与えたか
- 評価基準を明確にし、客観的な記録を残しているか
- 本採用拒否の理由を明確に説明できるか
- 就業規則に定められた手続きに従っているか
安易な本採用拒否は、不当解雇として訴えられるリスクがあります。実際に、裁判で企業側が敗訴する事例も多く見られます。
試用期間中の有給休暇はどうなるのか
試用期間も勤続期間に含まれる
年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます(労働基準法第39条)。
試用期間も勤続期間に含まれるため、入社日から6ヶ月後に有給休暇が発生します。
試用期間中の有給取得制限について
会社が入社時に有給休暇を前倒しして付与している場合、労働者から申請があれば原則として取得可能です。
雇用契約で「試用期間中は有給が使えない」としている場合でも、法的効力は限定的と考えられています。
計画的付与で有給休暇を取得させる場合は、入社6か月以内のスタッフの取り扱いをどうするのかを決めておく必要があります。
その他のよくある誤解と注意点
誤解1:本採用拒否は、試用期間の満了までに行えばいい
❌ 間違い:本採用を拒否する場合は、試用期間が終わるまでに通知すればいい
✅ 正解:試用期間中の本採用拒否であっても、入社から14日を経過している場合は、解雇と同じ手続きが必要です。
誤解2:試用期間を短くすれば社会保険に入れなくて済む
❌ 間違い:試用期間を2ヶ月以内にすれば社会保険に加入させなくて良い
✅ 正解:本採用を前提とした試用期間の場合、期間に関わらず入社日から社会保険加入義務があります
社会保険に「例外的に加入不要なケース」でご紹介済みですが、”2ヶ月という期間”に関して社会保険に加入しなくてもよいのは、「契約期間が2ヶ月以内で、延長の見込みがない短期雇用契約の場合」です。
社労士が教える試用期間運用の労務管理ポイント
就業規則への明記が必須
試用期間を設ける場合は、以下の内容を就業規則と雇用契約書に明記する必要があります。
- 試用期間の長さ
- 試用期間中の労働条件(給与、勤務時間など)
- 本採用の判断基準
- 試用期間の延長に関する規定
評価基準の明確化と記録保存
本採用を判断する際の評価基準を明確にし、試用期間中の勤務状況や指導内容を記録として残すことが重要です。
万が一、本採用拒否でトラブルになった際に、客観的な証拠として活用できます。
口頭で注意や指導をしたけれども、記録は残してない。というケースが多いです。きちんと書面(本人が受領した旨の署名や記名押印があると尚良し)やメールなど、記録が残るようにしましょう。
労働条件通知書の作成
労働基準法第15条により、雇用契約時には労働条件を書面で明示する義務があります。
試用期間中の条件も含めて、明確に記載した労働条件通知書を交付しましょう。
法的には労働条件通知書でも問題ありませんが、できる限り「雇用契約書」での労働条件の明示をおすすめします。
労働条件通知書・・・事業主側からの一方的な通知
雇用契約書・・・事業主と労働者の合意
小規模事業所特有の注意点
従業員20名以下の小規模事業所では、以下の点に特に注意が必要です。
- 常時10人以上の従業員がいる場合は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が必要
- 10人未満でも、トラブル防止のため就業規則を作成することが望ましい
- 社会保険の加入手続きは期限内に確実に行う
まとめ:試用期間の正しい理解で働きたくなる組織へ
本記事では、試用期間の正しいルールについて詳しく解説しました。
重要ポイント
- 試用期間中も正式な労働契約が成立しており、自由に解雇できるわけではない
- 試用期間の長さは3〜6ヶ月が一般的で、1年を超えると無効になる可能性がある
- 給料は最低賃金以上が必須で、残業代も支払う必要がある
- 試用期間中でも、入社日から社会保険への加入義務がある
- 本採用拒否には客観的に合理的な理由が必要で、事前の指導と記録が重要
- 就業規則と労働条件通知書(雇用契約書)への明記が必須
神戸市の小規模事業所の皆様が、正しい知識に基づいて試用期間を運用することで、お互いが納得できる雇用関係を築き、自分もスタッフも働きたくなる組織づくりを実現できます。
不明な点や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
🎯 試用期間の運用でお困りの方へ
無料相談実施中!
✅ 就業規則の試用期間規定が適切かチェック
✅ 社会保険加入の手続き支援
✅ 労務トラブル予防のアドバイス
【神戸市の小規模事業所様向け特別サポート】
初回相談無料
「試用期間中の社会保険手続きが分からない」
「本採用拒否を検討しているが法的に問題ないか確認したい」
「就業規則の試用期間規定を見直したい」
こうした組織づくりの課題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。